『スモールワールド』は、多様な種族とスキルの組み合わせでエリアを支配する戦略的ボードゲーム。この記事では、発売から15年が経過した現在でも『スモールワールド』が遊ぶ価値のある作品なのかを、人気レビュー動画の内容をもとに徹底検証します。
『スモールワールド』の概要
| 参加人数 | 2~5人 |
| プレイ時間 | 40~80分 |
| 対象年齢 | 8歳から |
| 発売時期 | 2009年~ |
| メカニクス | エリアマジョリティ(陣取り)/ダイスロール/プレイヤー別固有能力 |
| ゲームデザイン | フィリップ・キーヤーツ(Philippe Keyaerts) |
『スモールワールド』は、2〜5人(拡張で最大6人)で楽しめるエリアコントロール型のボードゲームです。プレイヤーは種族と特殊能力の組み合わせを選び、そのユニットを使ってマップ上の領地を征服し、最も多くの勝利点を獲得したプレイヤーが勝者となります。
ゲームは数ラウンドに渡って進行し、プレイヤーは必要に応じて「衰退(ディクライン)」を選ぶことで、新たな種族で再スタートすることができます。
:strip_icc()/pic428828.jpg)
:strip_icc()/pic449953.jpg)
レビュー:『スモールワールド』の魅力と限界
多彩な組み合わせが生む“繰り返し遊べる楽しさ”
本作の最大の魅力は、種族とスキルの組み合わせが無限に近いバリエーションを生み出す点です。
レビューでは、「ホールディング・ハーフリング」や「フライング・ソーサラー」など、組み合わせによってプレイ感がガラリと変わる点を高く評価。拡張セット(例:Underground, Realmsなど)を導入すれば、さらに多様性が拡大します。
プレイヤー数ごとの専用マップでスケーラビリティも高い
人数に応じて異なるマップが用意されており、2人でも6人でもバランス良く遊べるデザインとなっています。レビューでは、「人数によって盤面を制限するタイプのゲームと比べて好印象」とコメント。
また、リアルムズ拡張を使えば、モジュール形式で自作マップも構築可能です。
中盤以降に訪れる“避けられない衝突”がゲームに緊張感を与える
序盤は拡張フェーズ、中盤以降は衝突が避けられない構造になっており、エリアコントロールゲームらしい駆け引きが終盤にかけて本格化していきます。
ただし、「序盤は淡々と進みがち」「中盤から急激にコンフリクトが増える」といったテンポ面への言及もありました。
レビューにおける批判的な視点
選択肢が少なくなりがちで戦略が単調になる
レビューでは、「プレイが進むほどに選択肢が狭まり、自由度が減る」という指摘も。特に周囲を他プレイヤーに囲まれると、移動・攻撃の自由度が極端に低下します。
強すぎる組み合わせによるゲームバランスの崩壊
一部のコンボ、例として「フライング・ソーサラー」や「多数ユニット系のラット族+商人」などが、ゲーム全体のバランスを大きく傾ける可能性があるとされています。
他プレイヤーがその組み合わせを取った瞬間に、「手も足も出ない」と感じる場面があることは否定できません。
プレイ時間とダウンタイムが長くなりがち
特に4人以上でのプレイ時には、考えすぎによるターン遅延(ダウンタイム)が大きな問題になると述べられています。特にライトなルールに対して、悩む時間が長くなるとテンポが損なわれます。
『スモールワールド』は今なお遊ぶ価値があるか?
総評として、レビューは「過去の名作としての地位は揺るがないが、現代の新作ゲームと比べるとやや見劣りする」と結論づけています。
例えば『Blood Rage』や『Rising Sun』といった現代のエリアコントロール系作品は、より高度な選択肢と緊張感を備えており、『スモールワールド』が持つ「配置して得点を得る」スタイルはやや古臭く映るかもしれません。
こんな人におすすめ
- コンボ好き、バリエーションを楽しみたい人
- 中軽量級のエリアコントロールゲームを探している人
- 家族やボードゲーム初心者と幅広く遊びたい人
まとめ:『スモールワールド』は“進化した今でも光る基礎作品”
『スモールワールド』は、シンプルなルールと多様な組み合わせによる戦略の自由度で、多くのプレイヤーに愛されてきた名作です。
ただし、現代の複雑でテンポ感のあるエリアコントロールゲームと比べると、戦略性やテンポ面で一歩劣るという印象も。
それでも、初級者から中級者へのステップアップとして最適な作品であることに疑いはありません。シンプルさとバリエーションの豊富さが見事に融合した本作を、ぜひ一度プレイしてみてください。
このゲームは↓の記事でもオススメされています!
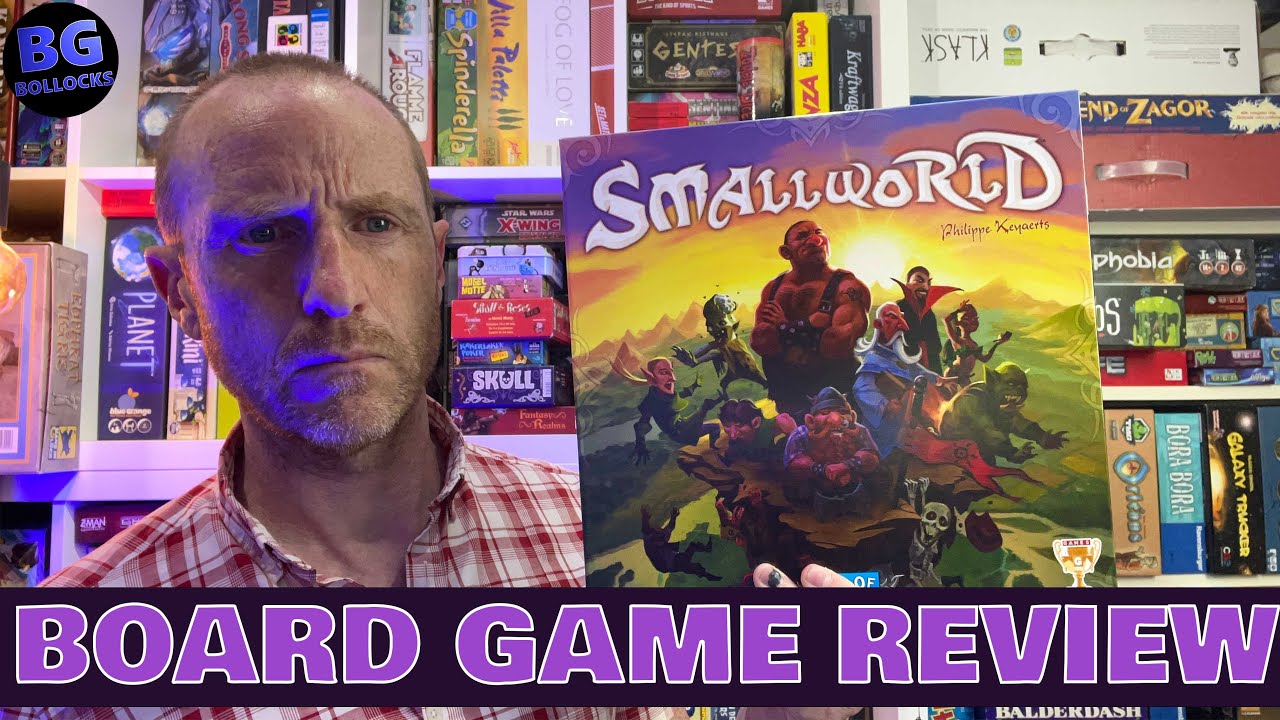

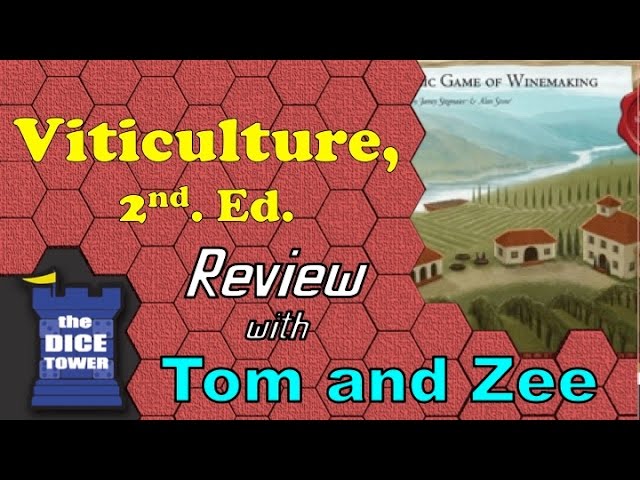

コメント