ボードゲームギーク(BoardGameGeek)おすすめボドゲ
この記事は、YouTubeチャンネル「Board Game Geek」が公開した動画「Top 5 Games for August 2025」を元に、注目のトリックテイキング(取り札)ゲーム5作を日本語で丁寧に解説したものです。
動画ではホストが実際のプレイ感を交えて紹介しており、それぞれの魅力や向き不向き、遊ぶときのポイントを語っています。
本記事ではルールは簡潔に抑えつつ、各ゲームの“遊び心地”に重点を置いたレビューを行います。
1. キャット・イン・ザ・ボックス(Cat in the Box)
概要
『キャット・イン・ザ・ボックス』は、カードの色が事前に決まっておらず、プレイヤーがカードを出す瞬間に「そのカードは何色か」を宣言してから場に置くという独自の仕組みを持つトリックテイキングです。
各プレイヤーは共通のボード上に自分のトークンを配置し、宣言した「色×数字」のセルを占有していきます。占有が大きな塊になると得点が増える一方で、自分の過去の宣言が後々の選択肢を縛り、場合によっては宣言の矛盾(パラドックス)を起こしてしまうことがあります。
つまり、色を自由に宣言できる反面、その自由が自分にも他人にも負担をかける、という二重構造がゲームの核となっています。



※公式サイトである ホビージャパン公式ページより引用しています。画像の著作権は権利元に帰属します。
感想
このゲームの最大の魅力は、「色を自分で決める」という発想が生む独特の読み合い」です。従来のトリックテイキングでは、手札の色そのものが価値を決めるため、配られた瞬間に手の善し悪しがある程度見えます。
しかし本作では、同じ手札であっても「どのカードをどの色として使うか」で価値が大きく変わります。例えば、序盤で取っておきたい塊を作るためにあるカードを赤と宣言すると、中盤以降に青で出したい場面で手詰まりを起こすことがあり、短期的利益と長期的な戦略性の板挟みになります。
さらに、このゲームは「塊(エリアをつなげる)作り」と「パラドックス回避」の二つの要素が常に隣り合わせにあるため、得点を伸ばそうと攻めた結果、思わぬところで自分の首を絞める――というドラマが頻出します。
気をつけたい点としては、思考負荷が想像以上に高いことです。ルール自体は直感的ですが、「自分の今の宣言が将来にどう響くか」を常に想像し続ける必要があり、軽い気持ちのパーティ卓よりもある程度考えるのが好きなメンバー向けです。
また、初回は宣言とボードの占有ルールに慣れるまで時間が必要で、誤宣言や判定ミスが起きやすいので、ルール確認がしっかりできる人がいるとスムーズに遊べます。
総合すると、『キャット・イン・ザ・ボックス』はトリックテイキングのルールを大胆にひっくり返して新たな読み合いを生み出した作品で、「カードの価値を自分で作る」楽しさを味わいたい人に特におすすめです。
↓の記事でもっと詳しくレビューしています!
2. レベル・プリンセス(Revel Princess)
概要
『レベル・プリンセス』はハーツ系の「失点を避ける」基本構造を土台に、各ラウンドで追加される“日替わりルール”や、プリンセス/プリンスなどのキャラクター固有能力を組み合わせて変化を作るゲームです。
基本の目標は失点を抑えることにありますが、特定の状況では「全部取って逆転する(シュート・ザ・ムーン型)」のも有効で、キャラクターの特殊効果が戦略の幅を広げます。


感想
『レベル・プリンセス』は、トリックテイキング入門として非常に優れた側面を持っています。まず、基本ルールは馴染みのある「失点を避ける」方式なので、ハーツに慣れた人なら直感的に動けます。そこに毎ラウンド追加される特殊ルールやキャラクター能力が入ることで、同じゲームを何度やっても「今日はどんな展開が来るか」というワクワク感が保たれます。
動画のホストが語るように、「プロポーズ(特定の失点)」を避けつつチャンスがあれば逆転も狙う――という駆け引きが何度も発生し、テーブルは自然と盛り上がります。
遊んでみると、キャラクター能力の取捨選択が勝敗に直結する瞬間が多く、短期的判断と中長期的プランニングの両方を同時に考える楽しさがあります。例えばあるラウンドでは「このキャラの能力を活かすためにあえて危ない札を残す」といった戦術が有効で、成功すると派手な逆転劇が起きます。これが家族卓やパーティー卓でウケる大きな理由です。
総評として、『レベル・プリンセス』はトリックテイキングの楽しさをそのまま残しつつ、小さな変化で毎回の卓を新鮮に保つことに成功しています。
ライトに遊びたい家族や、トリテの導入を考えている友人に薦めやすい一方、ゲーマーが望むような深い読み合いだけを求めると物足りなさを感じるかもしれません。
しかし「程よい読み+笑い+逆転」が欲しい場には非常にマッチするタイトルです。
↓の記事でもっと詳しくレビューしています!
3. 波乱と海原(Seas of Strife)
概要
『波乱と海原』は、通常のトリックテイキングと違い「その場で最も多く出たスート(同じ種類のカード)がリード扱いになる」独特のルールを持つゲームです。
そのため、あなたが安全に捨てた札が他のプレイヤーの出目によって一転して“勝ち札”に変化することがあり、受け身のプレイが通用しにくい設計になっています。
結果として、回避(誰に取らせるか)を中心にした独特の駆け引きが生まれます。
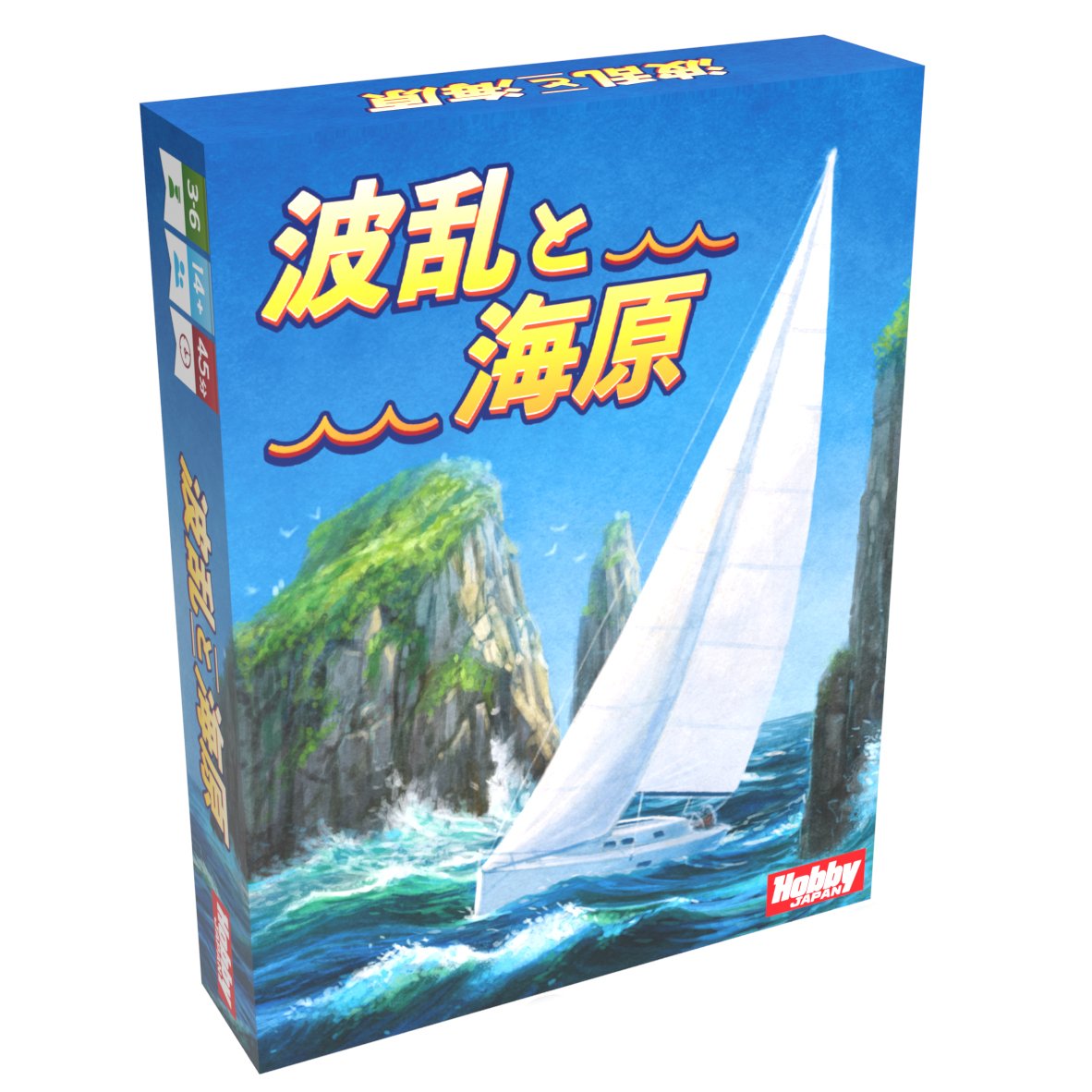
感想
このゲームの面白さは、“場の多数派を読む”ことに重心がある点です。従来のトリックテイキングでは「自分が勝ちたければ強いスートを出す/負けたければ弱い札を出す」といった直感が通用しますが、本作では他のプレイヤーが何をどれだけ出すかによって一瞬で状況が逆転します。つまり、「今持っている弱い札が、誰かの出し方次第で一気に危険牌に変わる」ため、単純に弱いカードを投げ捨てればいいという思考は通用しません。
プレイしていると、最も多く出るスートを想像する高度な読み合いが求められます。自分の脱出口を作るために敢えて相手の動きを誘導するプレイが生まれ、無言の共謀や牽制がテーブル上で起こります。
この「押し付けて取らせる」快感は独特で、うまく成功したときのテーブルの反応はとても盛り上がります。動画のホストも「取らせられた瞬間の喜びと悲鳴」がこのゲームの魅力だと繰り返し語っていました。
一方で、ゲームの性質上「回避」が中心となるため、得点としての派手さが控えめに感じられる人もいるでしょう。勝利は派手に得点が跳ね上がるよりも、細かな回避の蓄積によって成される傾向があります。したがって、すぐにわかる派手な逆転劇を好む層には物足りない可能性がありますが、「短期的な読みの正確さを競う」タイプの遊びが好きなら非常に面白く感じられるはずです。
↓の記事でもっと詳しくレビューしています!
4. スカルキング(Skull King)
概要
『スカルキング』はビッド(予想)を行い「ぴったり取る」ことを狙うトリックテイキングで、海賊や人魚、特殊効果カードといったテーマ要素が加わったパーティ向けの人気作です。ビッドが当たれば大きく得点、外せば失点というハイリスク・ハイリターンの得点構造が特徴で、多くの拡張的効果がゲームをにぎやかにします。


※この記事で使用している画像は、公式ショップページより引用しました。詳細はこちらのページをご覧ください。画像の著作権は 店舗または権利元に帰属します。
感想
『スカルキング』は、ビッド制トリックテイキングの王道にテーマ効果を巧みに乗せた作品で、初めてトリックテイキングを遊ぶ人から熟練者まで広く楽しめる魅力を持っています。
まず、ビッドの読み合いが生む一瞬一瞬の緊張感が非常に心地よい点が挙げられます。自分が何トリック取るかを宣言して、それが当たると大きな報酬が入り、外れると痛いペナルティが入る――この刺激的な構造がラウンドごとに波を作り、テーブルの緊張と笑いを両方生み出します。
さらに特殊カード(スカル、スカルキング、海賊、海の怪物など)がゲームの戦術性を高めています。これらのカードは単に強い・弱いというだけでなく、ビッド戦略に対する“工具”として機能します。
たとえば自分が少しでもビッドを外されそうだと感じたときに特殊カードでラインを崩す、逆に一発勝負で大勝ちを狙う時にそれを温存する、といった判断が生まれます。
総じて、『スカルキング』は「読みと演出」を両立させたパーティ寄りの傑作です。戦術ゲームとは別の方向を向いていますが、ビッドの緊張感を手軽に味わいたい場には最適で、初めて購入するトリックテイキングタイトルとしても優秀です。
↓の記事でもっと詳しくレビューしています!
5. ザ・クルー:第9惑星の探索(The Crew: The Quest for Planet Nine)
概要
『ザ・クルー:第9惑星の探索』は協力型トリックテイキングで、プレイヤーは会話制限の中で順番にミッションを達成していきます。
各ミッションは達成条件が異なり、カードの出し方で仲間に情報を間接的に伝え合う独特のコミュニケーションが求められます。ミッションは段階的に難しくなり、短時間の連続プレイで達成率を上げていく設計です。


※この記事で使用している『ザ・クルー:第9惑星への旅』の画像は、公式メーカーであるジーピーゲームズによる製品紹介ページより引用しています。詳細は こちらのページをご参照ください。画像の著作権は権利元に帰属します。
感想
レビューで触れられている通り、このゲームの魅力は「短いミッションを重ねることで上達が実感できる」点です。最初のうちはミッションを失敗してしまっても、次に同じような条件が来たときに前回の反省を活かしてプレイできます。これは協力ゲームとして非常に重要な要素で、プレイヤー同士の信頼や読みの精度が向上していく過程が楽しめます。
注意点としては、会話を制限されるストレスを楽しめない人には向かない点です。特にリーダー役となる人は、伝えたいことを口にできないもどかしさに悩む場面があるかもしれません。
また配牌の運によってはどうしても達成が難しいミッションに当たることがあり、その場合はチーム全員で方針を調整してリトライする柔軟性が求められます。それでも、失敗しても次がある構成になっているため、挫折感が残りにくいのは親切な設計です。
まとめると、『ザ・クルー:第9惑星への旅』は単なるトリックテイキングでは味わえない「共闘の喜び」を提供する作品です。プレイを重ねるごとにチームの意思疎通が上達していく感触は強烈で、協力ゲーム好き、あるいはトリテの新しい可能性を体験したい人には強くおすすめできます。
↓の記事でもっと詳しくレビューしています!
まとめ:あなたに合うトリテはどれか?
今回取り上げた5作はすべて「トリックテイキング」という共通土台を持ちつつ、ルールのどこを変えるかで体験が大きく異なります。
思考の深さを楽しみたいなら『キャット・イン・ザ・ボックス』、家族やカジュアル卓での盛り上がりを重視するなら『レベル・プリンセス』『スカルキング』、読みと回避の妙味を味わいたければ『シーズ・オブ・ストライフ』、協力でパズルを解く楽しさを追求するなら『ザ・クルー』が向いています。
動画の紹介は実プレイに基づいた生の感想が多く、どの作品にも独自の魅力があるため、まずは自分のプレイスタイルに合いそうな一本を試してみるのがおすすめです。


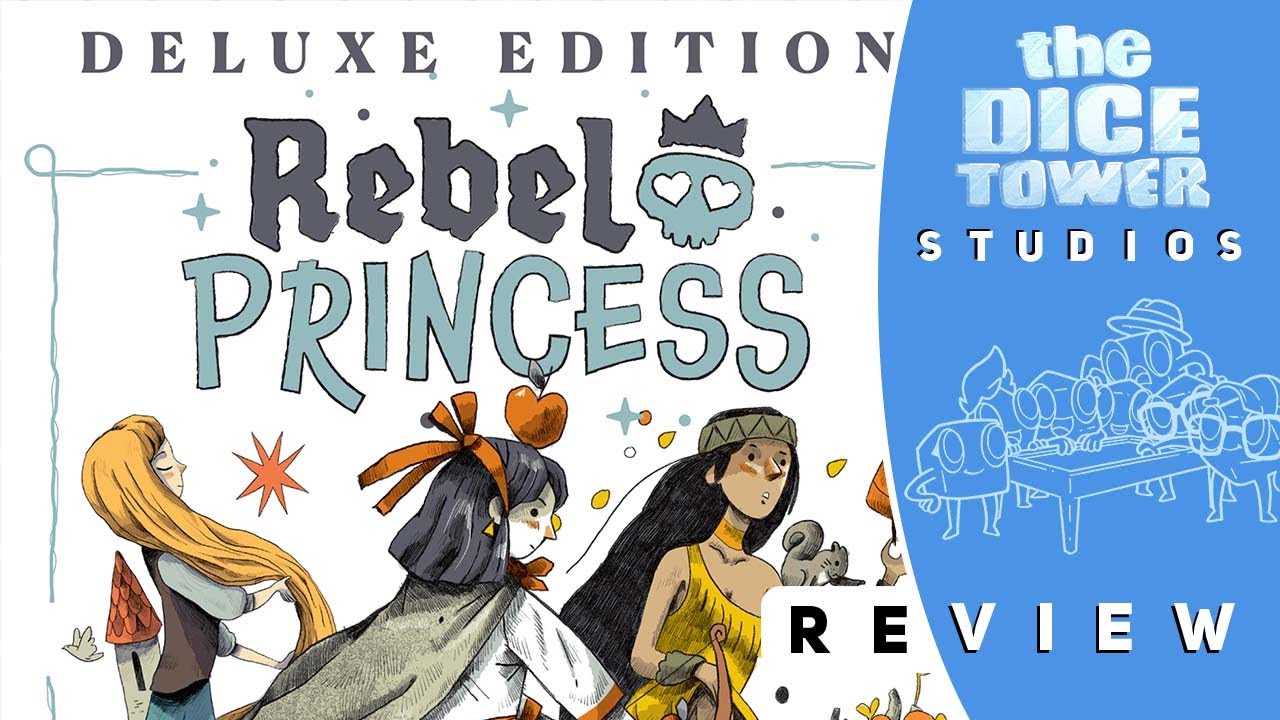
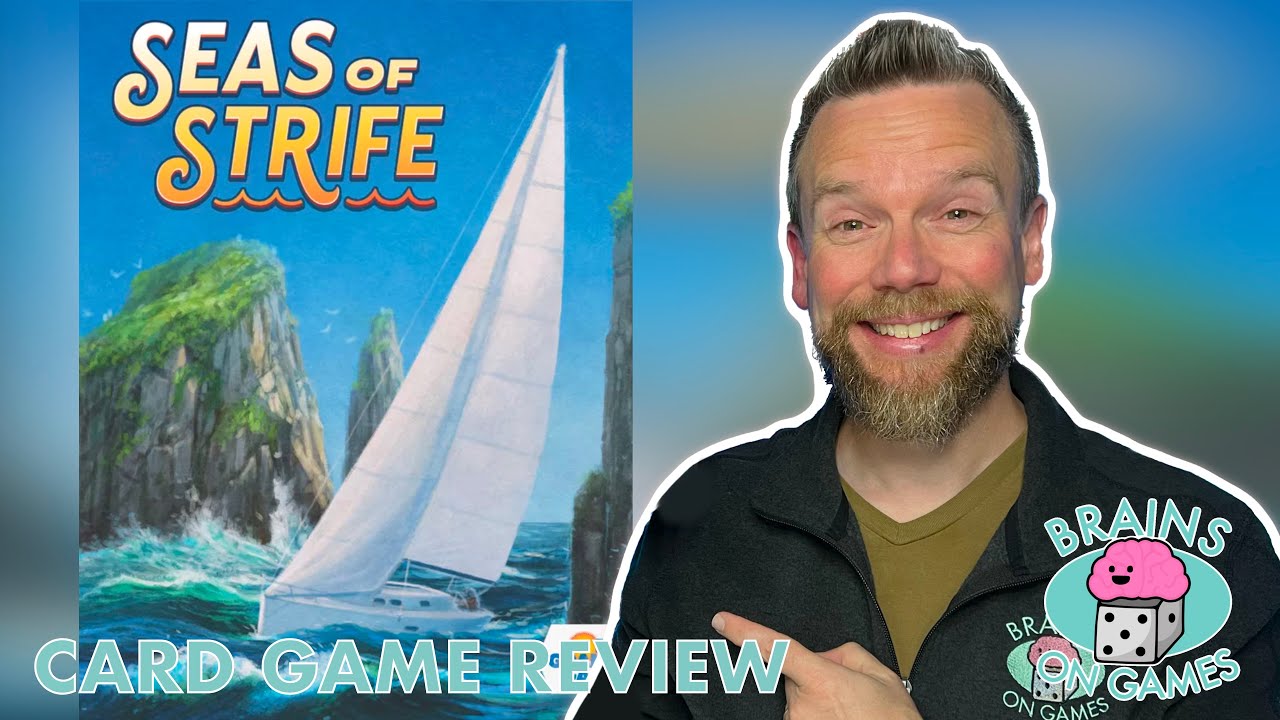

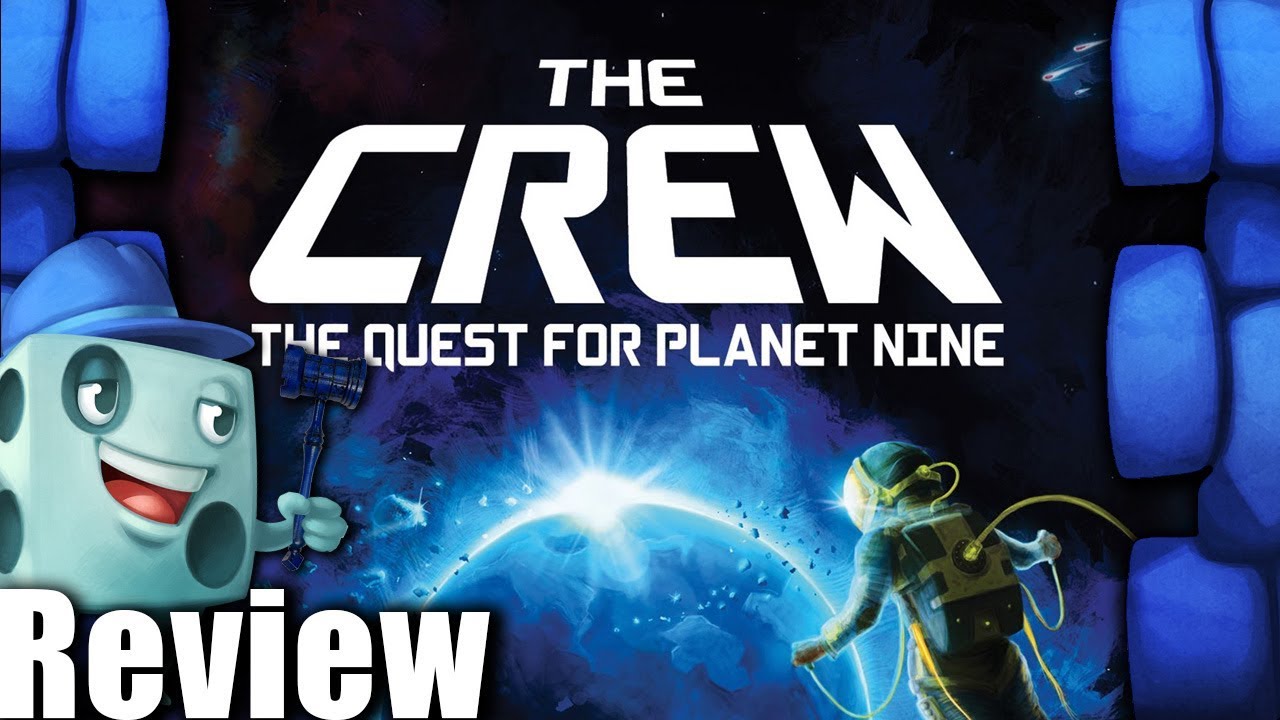
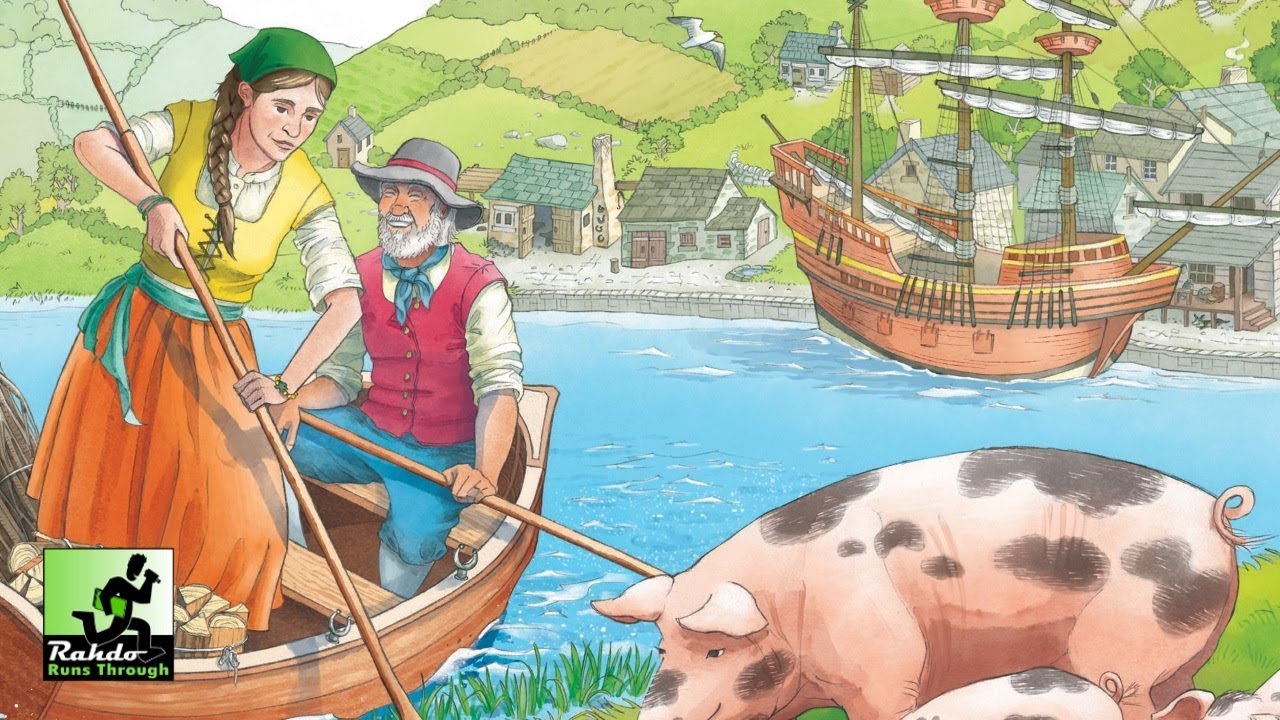
コメント