Tom Vasel氏、Wendy Yi氏、Chris Yee氏、Mike Delisio氏が出演する「Wayfarers of the South Tigris Review – Land & Water & Space Oh, My!」の動画では、シェム・フィリップスによる三部作の第1作目「南チグリスの旅人」を紹介しています。
本記事では動画の要点をもとに、ダイスをワーカーとして活用するメカニクスや、ランド・水路・天空を探検するテーマの魅力、プレイ感を詳しく解説します。
結論
「南チグリスの旅人」はダイス配置を通じて自分だけのカードエリアを広げるユニークな体験を味わえます。テーマを感じさせるビジュアルと、トラックを巡る駆け引きが見事に噛み合い、繰り返し遊んでも新鮮です。
情報量は多いものの、慣れれば爽快な選択が積み重なる快感が得られる一作と言えます。
ゲームの概要
| 参加人数 | 1~4人 |
| プレイ時間 | 60~90分 |
| 対象年齢 | 12歳から |
| 発売時期 | 2022年~ |
| メカニクス | タイル配置/エリアマジョリティ/モジュラーボード/セットコレクション/ドラフト/ダイスプレイスメント |
| ゲームデザイン | SJマクドナルド(S J Macdonald)/シェム・フィリップス(Shem Phillips) |
プレイヤーは地図製作者となり、陸路・水路・天空の各カードを自分のボードに配置して拡大していきます。アクションは「ダイス配置」「ワーカー配置」「休息」の3種類。配置時には必要なタグ(ラクダ・望遠鏡・タコなど)をダイスやカードで満たしつつ、銀貨や補給物資を獲得したり、新たなダイスを増やしたり、ジャーナルトラックを進めて改良タイルを得たりします。
最終的にジャーナルトラックでゲーム終了が告げられ、セットコレクションやスペースカード、カルバン得点、ギルド多数点などで競い合います。


感想
コンポーネントとアートワーク
まず陸路・水路・スペースの3層構造のカード群が眼を引きます。特に天空カードの背景は濃密な星空が広がり、シリーズ随一の美しさ。カードを並べる自分の「地図」がパノラマのように完成していく感覚はまさに圧巻です。
ただし、これだけのビジュアルを広げるには相当なテーブルスペースが必要で、狭い場所だと配置に苦労しそうでした。
ダイスの運用とキャラ要素
ダイスは単なるランダマイザーではなく、キャラごとに初期タグがあり成長させて配置に使うワーカーです。タグの獲得はトラック報酬やカードのおかげで多様性が高く、狙った配置スペースにスムーズにダイスを置けたときの達成感は格別。
ダイス目に応じたコストや報酬が明確で、1~3の小さな目も「先行権」「追加ダイス獲得」など用途がある点も秀逸でした。
トラックとゲームのテンポ
トラックの最右端に最初に到達したプレイヤーがゲーム終了を宣言する仕組みが緊張感を生みます。自分の手番でどれだけトラックを進めるか、先行して終了条件を満たすか、他者に遅れを取らないか――この読み合いが毎ラウンドの焦点になります。
多数の選択肢があるため初回は進行に戸惑いますが、2~3プレイで操作感がつかめ、90~120分で程よいリズムで遊べました。
インタラクションと競争感
直接の妨害要素は控えめですが、ダイス配置スペースに他者の色が増えるほどコスト(銀貨・補給物資)が高まる仕組みで、間接的な駆け引きが生まれます。
ギルドでの多数派争いもスリリングで、カード影響力を奪い合う瞬間は熱いものがあります。ただし、交戦シーンや手番干渉を好むプレイヤーには物足りないかもしれません。
リプレイ性とバリアント
カードプールが豊富かつ配置ルートを変えられるジャーナルバリアントや河道変更モジュールなど、何度遊んでも悩みどころが変化する設計です。
プレイごとに異なる陸路・水路・天空カードの組み合わせと、ギルド影響力の取り合いで毎回手応えが違い、長く遊べる点が高評価。ソロ用コンポーネントも同梱され、一人でもじっくり研究できます。
総合評価
「南チグリスの旅人」は美しいビジュアルと多彩なダイス活用、終盤のレース感を兼ね備えた中・重量級ユーロゲームです。情報量の多さは初回のハードルですが、慣れれば選択肢の連鎖が生む快感に夢中になります。
テーブルスペースや学習コストを許容できるなら、シリーズファンはもちろん、ダイスを資源に扱う新鮮さを求めるゲーマーにもぜひおすすめしたい一作です。
このゲームは↓の記事でランクインしています!


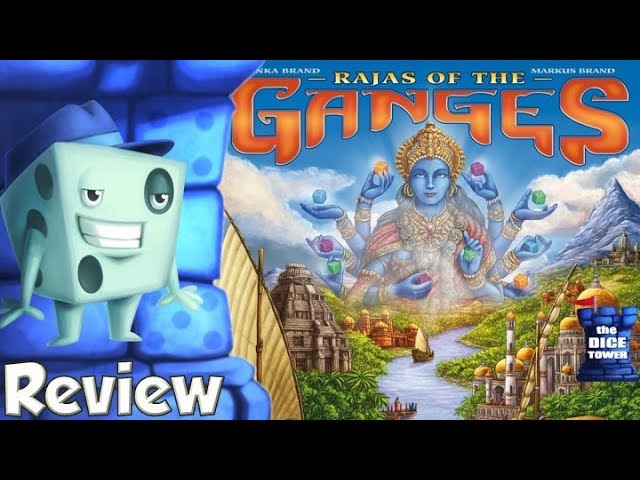
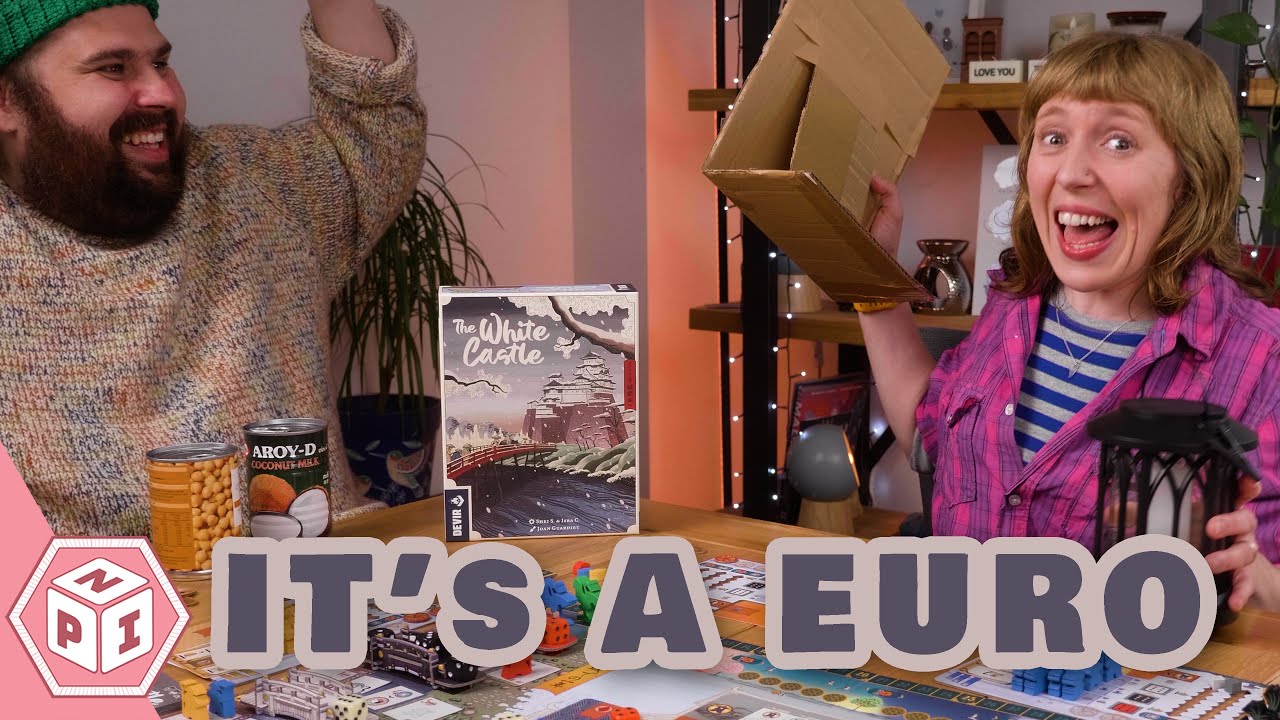
コメント