『南チグリスの学者』は、Garfield Gamesの南チグリス三部作第2作目として登場した、珍しい<翻訳>テーマのボードゲームです。
YouTube動画「Scholars of the South Tigris Review: Translate This!」が実演を交えて紹介した内容をもとに、翻訳者を雇い巻物を運ぶ独特のゲーム体験と、その戦略性・リプレイ性をわかりやすくまとめました。
遊び方の要点と、プレイ後に感じた魅力・課題を解説します。
結論
『南チグリスの学者』は、巻物の翻訳という新鮮なテーマと、ドラフト+ダイス+ワーカープレイスメントが融合したメカニクスが特徴です。
多彩なアクションを駆使してポイントを稼ぎ、最終得点で勝者を決める流れは安定感があります。
ソロモードの完成度が高く、最大3人プレイでほどよい駆け引きが楽しめますが、豊富すぎるアイコンと考慮事項がやや重く感じられる場面もあり、初回は慣れが必要です。
ゲームの概要
| 参加人数 | 1~4人 |
| プレイ時間 | 60~90分 |
| 対象年齢 | 12歳から |
| 発売時期 | 2023年~ |
| メカニクス | エリアマジョリティ/ハンドマネジメント/デッキビルディング/ロンデル/ダイスプレイスメント |
| ゲームデザイン | SJマクドナルド(S J Macdonald)/シェム・フィリップス(Shem Phillips) |
各プレイヤーは「翻訳者」を雇い、巻物を届けて翻訳する商人となります。ゲーム開始時に、ダイス(労働者)と金貨・銀貨といったリソースをドラフトし、プレイヤーボードを準備します。
手番ではアクションカードにダイスを配置し、
- 「翻訳者の雇用/解雇」
- 「巻物の獲得」
- 「技術研究トラックの進行」
- 「巻物の翻訳」
- 「追加ボーナス獲得」
の中から最大2つのアクションを選択。特定のカードを翻訳すると最終得点源となり、3枚目の特殊カードでゲーム終了を誘発。
終了後に各自の翻訳巻物や研究進行度を合計し、最も高い得点を獲得したプレイヤーが勝利します。



感想
1. 翻訳テーマとメカニクスの親和性
巻物を母語からアラビア語に翻訳するというテーマは非常にユニークです。翻訳者を雇う度に色付きダイスが追加され、それを使って直結する言語から段階的に変換していく流れは、「言語の連鎖」を直感的に体感できる仕組みとしてよく機能しています。
ただ、翻訳チェーンを構築する際は参照表を頻繁に見る必要があり、初見時はやや手間を感じました。それでも、自分が育てた翻訳ルートで巻物を完成させた瞬間の達成感は格別です。
2. 多彩なアクションと選択の幅
アクションは「雇用/解雇」「移動」「研究」「翻訳」「追加ボーナス」と5種類。ダイスを1~2個配置するだけのシンプルな枠組みですが、どのダイスをどのタイミングで使うか、解雇して即時利益を取るか雇用して将来活用するか、研究トラックを先行させるか巻物を優先するかなど、常に二択以上の悩ましさがあります。
進行フェイズごとに山札から“CFPカード”が出るたびに終了が近づく緊張感もあり、計画性が求められる作りです。
3. アートとアイコンの印象
イラストはMEO氏らしい線画調で世界観に統一感がありますが、ワーカーやリソース、研究トラックなどアイコンが多種多様で、初回は何度もルールを確認しました。
色覚サポートは配慮されていますが、色の違いが微妙な箇所もあり、「黄色ダイスは袋、青ダイスは手札」など細かな使い分けを覚えるのが大変です。
4. プレイヤー数と思考時間のバランス
ソロプレイはリプレイ性が高く、他人のターン待ちがないため快適です。二人でも会場を取り合う場面は少なく、ゆったり楽しめますが、最も熱いのは三人プレイでしょう。
三人だと翻訳者の奪い合いや研究競争が程よい緊張感を生み、かつ手番外での待ち時間も許容範囲です。
一方、四人は一手一手の選択肢が増えすぎて思考時間が伸びるため、あまりおすすめできません。
5. 総合評価:好みを問う一作
『南チグリスの学者』は、翻訳テーマをメカニクスに昇華した意欲作です。テーマとの一体感、研究トラックの戦略性、翻訳達成時の喜びなど、独自の魅力を多く備えています。
一方で、アイコン数の多さや思考要素の濃さは、ライトプレイヤーにとっては負担に感じるでしょう。
重めの戦略ゲームが好きな方、Garfield Gamesのシリーズが好きな方には強くおすすめしますが、ルール習得に時間をかけたくない方は注意が必要です。
このゲームは↓の記事でランクインしています!
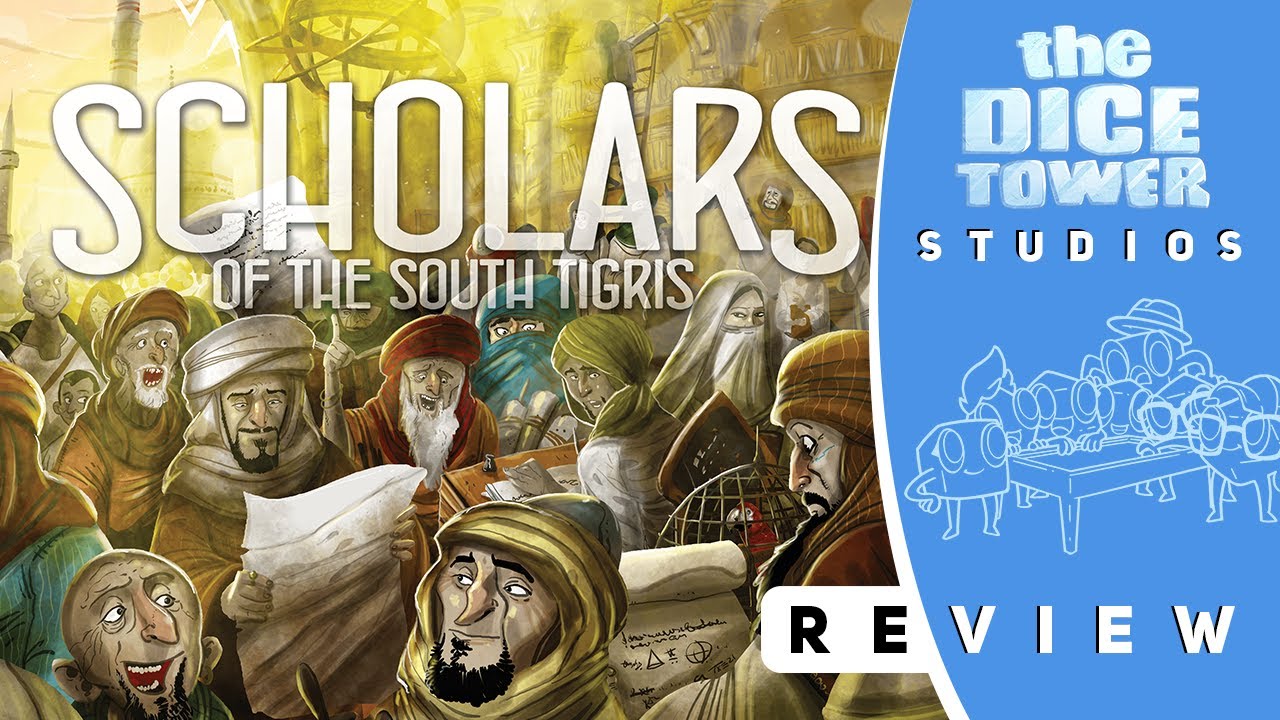


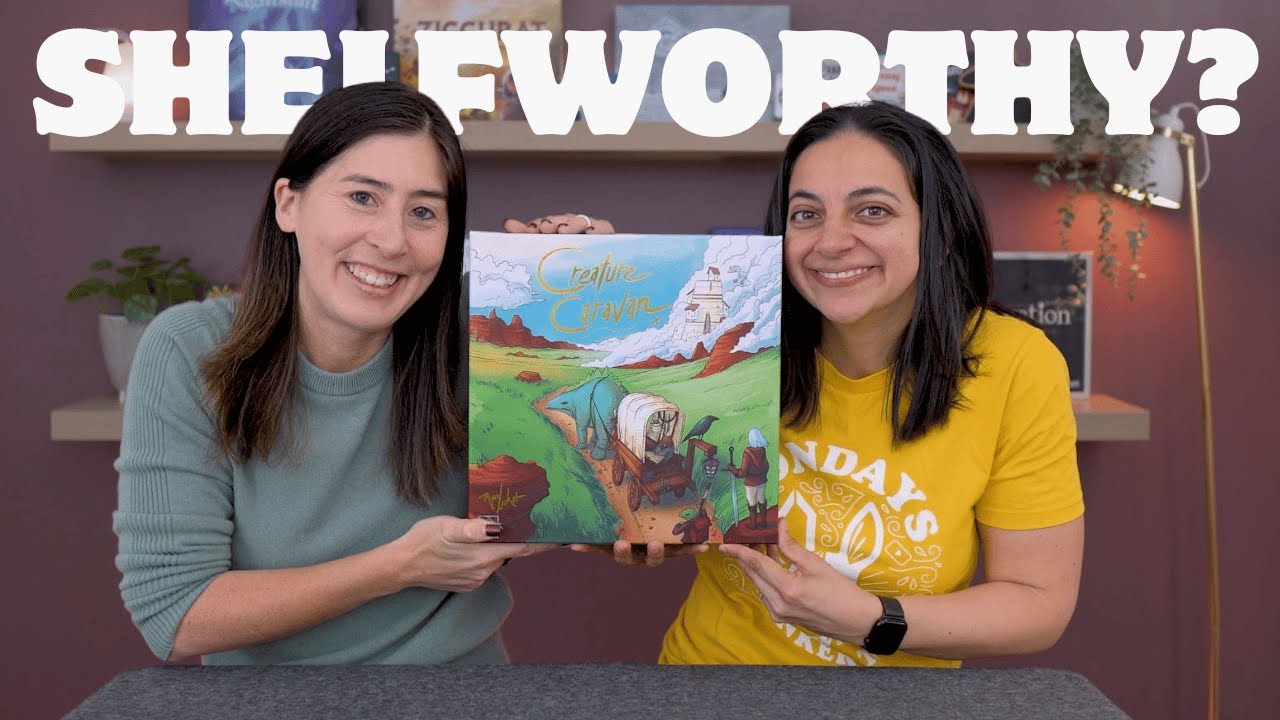
コメント