本記事では『テラミスティカ:革新の時代』について実際の遊び心地・魅力・気になる点を分かりやすく解説します。レビューでは、プレイヤーマット × 派閥タイルの“組み合わせ非対称”、従来の“カルト”に相当するトラック9段目以降の継続収入、そして新資源である「本(ブック)」の使い道が特に高く評価されています。
この記事では、これらの要点を踏まえつつ読みやすくまとめました。
結論(まず知ってほしいこと)
『テラミスティカ:革新の時代』は、慣れた手触りを保ちながら“選ぶ楽しさ”を大幅に増やした拡張進化型の本格ユーロです。特に、プレイヤーマットと派閥の組み合わせで生まれる多様性は、毎回の初期構成や戦略をガラッと変え、飽きにくさを強く後押しします。新資源「本」は最初こそ悩ましいものの、汎用リソースとして局面を押し広げる力があり、学習が進むほどプレイの幅が広がります。
一方で、シリーズ初見者には教えにくい・覚えることが多いというハードルも健在。総じて、テラミスティカ系を遊んできた人には強く勧めやすい一作です。
ゲームの概要
| 参加人数 | 1~5人 |
| プレイ時間 | 40~200分 |
| 対象年齢 | 14歳から |
| 発売時期 | 2023年~ |
| メカニクス | プレイヤー別固有能力 |
| ゲームデザイン | ヘルゲ・オシュテルターグ(Helge Ostertag) |
『テラミスティカ:革新の時代』は、地形を自分色に変える「開拓」→建設→都市化→トラック上昇→得点化を軸に、ラウンドごとの収入やラウンド目標、ボード下部の一回限りアクション(パワー消費)など、おなじみの流れを踏襲します。
その上で、
①プレイヤーマットと派閥タイルの組み合わせによる非対称化
②トラック9段目以降の継続収入追加
③新資源「本」の導入
といった新要素が加わり、構築と判断のレイヤーが厚くなりました。用語や細部は前作系統を踏襲しているため、シリーズ経験者なら短い説明で始めやすい一方、初プレイへのハードルはやや高めです。



感想
「組み合わせ非対称」が作る、毎回新しいスタート
まず強く感じたのは、プレイヤーマットと派閥タイルを“別々に選ぶ”設計の面白さです。片方が小さめの個性、もう片方がやや強い個性を持ち、それらが掛け算になって唯一無二の出力を生みます。
前作の「固定派閥=固定の手触り」に比べ、初期一手の重みと方針の決まり方がまるで違う。例えば、“森林系の色”に寄ったマットに“都市完成で一歩抜ける派閥”を重ねると、序盤から都市化の踏み込み方が変わります。これにより、セットアップ段階から既に楽しい。
同卓の4人が別の組み合わせを引くと、盤面の伸び方・資源の流れ・トラックの上がり方が目に見えて変化し、「今回はこの形」感がくっきり映し出されるのです。
9段目以降の“継続収入”が、トラック上昇の意味を塗り替える
従来のトラック(旧カルト)に、9段目以降での恒久的な収入が加わった設計は、とても上手い調整だと感じます。これまでは「鍵」や「終盤の多数決」など最終スコアへの貢献が中心でしたが、今作では“上げるたびに毎ラウンド効いてくる”という即効性が生まれます。
資源の系統(例:金、点数…など)がトラックごとに紐づくため、“この方針ならこの列を上げる”という戦略の筋道が立てやすい。序盤に少し無理してでも9段目を目指す価値が出て、プレイテンポが前のめりになります。
結果的に、盤面の手触りが「守り」より「攻め」寄りへシフト。これはシリーズ経験者ほど体感しやすい進化です。
新資源「本」が生む“悩ましさ”と“救済”
レビューでも語られている通り、得た瞬間に色を決める重みは、初プレイほど悩み深い。けれど、盤面下の一回限りアクションに“本を支払って強力な一手を引き出す”選択肢があるため、不要な手詰まりを救済するクッションとしても機能します。たとえば「本2冊で6金」「本1冊で5パワー回転」など、その場で局面を押し広げる即効薬が手に入るのは爽快。
色の決断に迷って消耗するより、“まずは本を集め、必要な場面で吐き出す”という学習も成立します。結果として、リソースの停滞が少なく、ラウンドごとに動きが出るのが好印象でした。
シリーズ経験があると最高、初見は手厚い導入が必須
レビューでも明言されているように、完全初見への教授は難度高めです。土台はテラミスティカ系そのものなので、基本概念(地形変換・建設・パワー経済・都市化・トラック)の共有があると、説明は一気に短く済みます。
逆に初見卓では、「まずは基礎版やテラノヴァを軽く」→「本作」という階段が現実的。入門を乗り越えた先の景色が広く、遊ぶほど選択が賢くなる喜びはこの系統ならではでしょう。
ラウンドの緊張感
ボード下の一回限りのアクションは、今作でも席取りのような緊張感を与えます。ここに「本」を絡めた選択肢が混ざることで、“通常収入では届かない背伸び”が可能になりました。
自分の手番で建物を先に差し込みたいのか、強力な下段アクションで急場をしのぐのか。盤面と下段の二正面作戦が常に悩ませます。特に、非対称の組み合わせで必要資源が微妙にズレるため、毎ラウンドの最適解が人によって変わるのが面白い。
結果、4人戦でも“待ち時間の退屈”が少ない感触がありました。
アートと没入感
盤面アート、とりわけ水辺の描写が非常に美しいという感想は強く共感できます。ルールの複雑さを支えるのは、視認しやすい配置・色分け・気持ち良いレイヤー構造です。
情報量が多いゲームにおいて、見た瞬間に意味が取れるグラフィックは、それ自体がプレイアビリティ。“考える体験”を邪魔せず、背中をそっと押す良いUIだと感じます。見た目の満足感がターンの疲労を緩和し、長めのプレイ時間を支える効果も見逃せません。
7. だれに刺さる?—おすすめと注意点
おすすめは、
テラミスティカ/ガイアプロジェクト/テラノヴァを何度か遊んだことがある人
初期構成から戦略が分岐する”タイプが好きな人
毎局面で微差を積むユーロの快感を求める人
いっぽう注意したいのは、完全な新規や、重めの思考と長時間プレイに慣れていない人。ただし、経験者が一人同卓にいるだけで学習コストは大きく下がるため、導入の工夫(事前の用語共有・序盤の方針例示)で十分カバー可能です。
総括:シリーズの“良い骨格”を残しつつ、現代的な伸びやすさを獲得
『テラミスティカ:革新の時代』は、過去作の蓄積を大切に守りながら、選択の自由度と中盤の伸びやすさを強化した作品です。とりわけ、非対称の再設計(組み合わせ)はリプレイ性のコアであり、9段目以降の継続収入は“上げ得”ではなく“方針と噛み合う投資”として機能。
「本」資源は、学習が進むほど“攻めのカード”になっていきます。重ゲーが好きな人には、“今っぽい手応え”で何度も卓に乗る一本として推せます。
このゲームは↓の記事でオススメなボドゲに選ばれています!



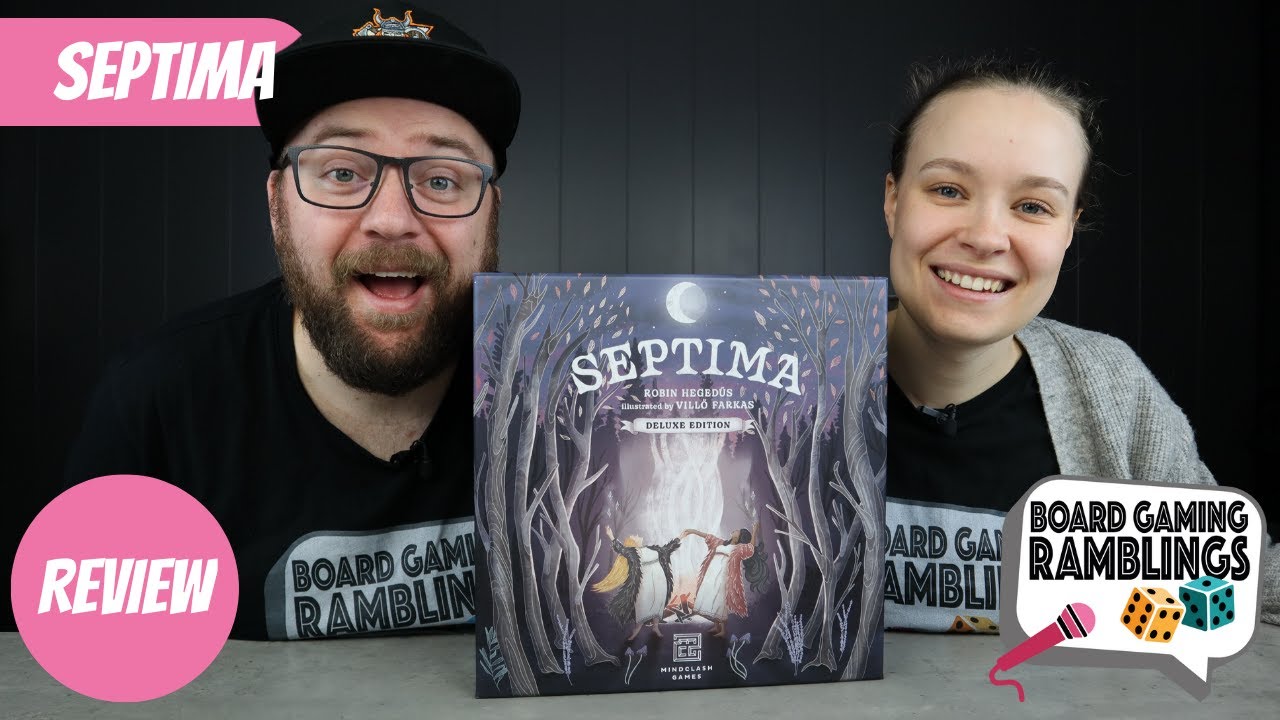
コメント